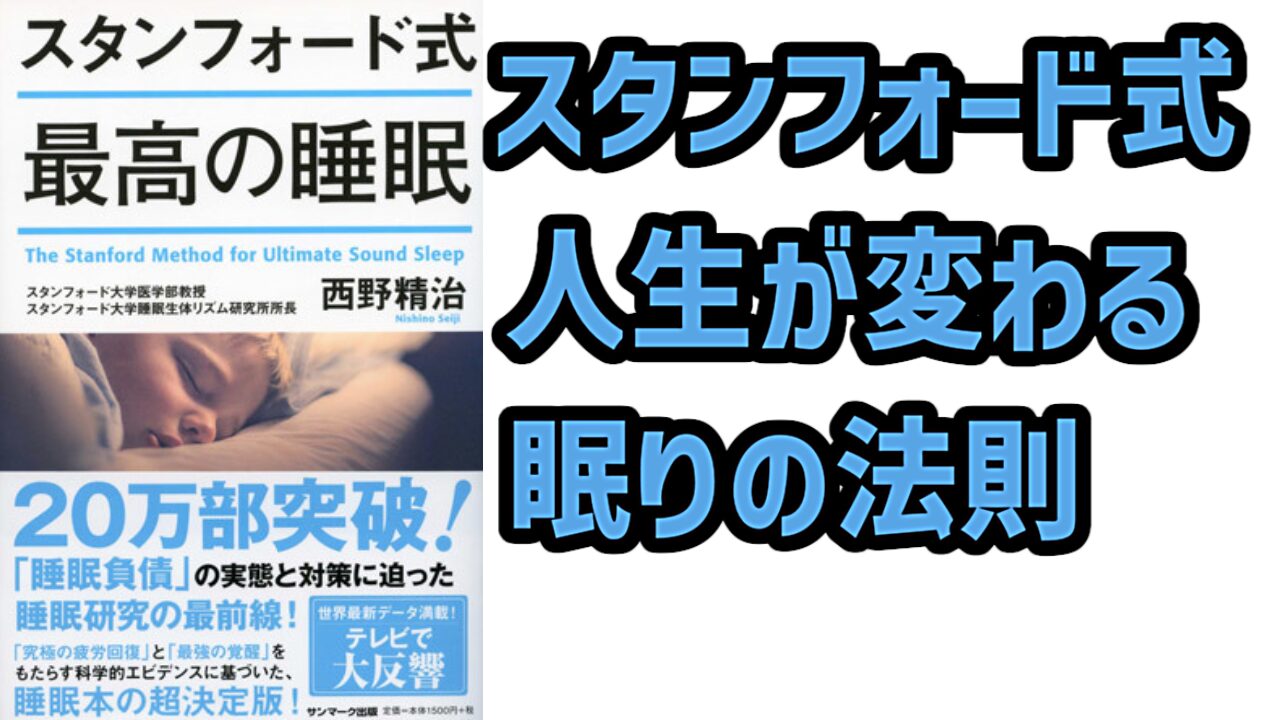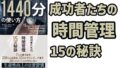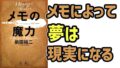あなたは本当に満足のいく睡眠をとれていますか?
あなたは、昨晩ぐっすり眠れましたか?
「眠れたような、眠れていないような…」「朝起きても疲れが取れていない」
そんな感覚を抱えたまま、日々を過ごしていないでしょうか?
実際、全米では現在2,000〜3,000もの睡眠クリニックが存在し、多くの人が「眠りの悩み」に直面しています。不眠症とまではいかなくても、「自分の睡眠に満足している」と胸を張って言える人は決して多くありません。
とくに多忙なビジネスパーソンにとって、睡眠はつい後回しにされがち。
これは、多くの現代人にとって共通の悩みではないでしょうか。
しかし、量を増やすことだけが正解ではありません。
そもそも、「最高の睡眠」とはなんでしょうか?
それは「脳・体・精神」を最高のコンディションに整える、「究極的に質の高まった睡眠」です。
本ブログでは、そんな「最高の睡眠」を実現するための知識と実践法を、『スタンフォード式 最高の睡眠』の内容をベースに、
わかりやすくまとめていきます。
睡眠に悩むあなたの、明日を変えるきっかけになれば幸いです。
世界一睡眠偏差値が低い国・日本
あなたは「睡眠負債」という言葉を聞いたことがありますか?
これは、『スタンフォード式 最高の睡眠』の中で登場するキーワードで、睡眠不足が慢性的に蓄積された状態を指します。
疲れが取れにくい。集中できない。気分が沈みがち。
これらの不調は、もしかすると眠りの借金が原因かもしれません。
そして、日本はこの睡眠負債を抱える人が世界で最も多い国のひとつです。
フランスの平均睡眠時間:8.7時間
アメリカの平均睡眠時間:7.5時間
そして日本は、わずか6.5時間
さらに深刻なのは、睡眠時間が6時間未満の人が全体の約40%にものぼるという事実。
ミシガン大学が2016年に行った国際調査では、なんと日本は100カ国中で最下位という不名誉な結果に。
これはつまり「日本人は、世界一寝ていない国民」だということです。
睡眠は、私たちの心と体を回復させる命綱のような存在。
それが足りていないという現実を、今こそ真剣に受け止めるべきときかもしれません。
次の項目ではそんな睡眠に課せられたミッションをまとめていきます。
睡眠に課せられた「5つのミッション」
ぐっすり眠った翌朝、あなたの脳と体はどんな状態ですか?
頭が冴えて、体が軽く、前向きな気分で1日をスタートできる.
これこそが「質の高い睡眠」がもたらす真の恩恵です。
では、眠っている間に脳と体では何が行われているのでしょうか?
『スタンフォード式 最高の睡眠』では、睡眠の果たすべき役割(=ミッション)を5つに整理しています。
このメカニズムを知れば、「なぜ睡眠が大切なのか?」がはっきりと見えてきます。
① 脳と体に「休息」を与える
まず、最も基本的な役割が休息。
私たちの体は、無意識のうちに自律神経によってコントロールされています。
昼間に活性化する「交感神経」
リラックス状態をつくる「副交感神経」
本来であれば夜になると副交感神経が優位になり、体も脳も休息モードへと移行します。
しかし、現代人は仕事・スマホ・ストレスなどの影響で交感神経が優位なまま夜を迎えがち。
その結果、寝付きが悪くなり、眠りが浅くなってしまうのです。
特に大切なのが、眠り始めの最初の90分。
このノンレム睡眠のタイミングでしっかり副交感神経が優位になることで、深い眠りと回復が得られます。
②「記憶」を整理して定着させる
睡眠中、私たちの脳はただ休んでいるわけではありません。
記憶の整理と定着という、非常に重要な処理を行っています。
ノンレム睡眠とレム睡眠を交互に繰り返すことで、日中に得た情報を取捨選択しながら整理し、長期記憶として保存します。
また、嫌な記憶や不要な情報を忘れることも脳の大事な仕事。
記憶のクリーンアップも、質の良い睡眠によって行われるのです。
③「ホルモンバランス」を調整する
ホルモンの分泌と調整も、睡眠の重要な役割のひとつ。
睡眠中には、成長ホルモンやメラトニン、コルチゾールなど、私たちの心身のバランスを保つホルモンが活発に働いています。
質の高い睡眠は、ホルモンの分泌リズムを整え、生活習慣病の予防・改善にも効果があるとされています。
④「免疫力」を上げて病気を遠ざける
風邪をひいたとき、「とにかく寝て治す」というのは理にかなった行動です。
なぜなら、睡眠中にホルモンバランスが整うことで、免疫システムの働きが強化されるからです。
逆に、睡眠が不足するとホルモンバランスが崩れ、免疫力も著しく低下。
病気への抵抗力が落ちることが、科学的にも証明されています。
⑤脳の老廃物を取る
睡眠の最後のミッションは、脳のメンテナンス。
脳は「脳脊髄液」という液体によって守られており、この液体が1日約4回(計600ml)ほど入れ替わると言われています。
この入れ替えの際に、脳に溜まった老廃物も一緒に排出されるのです。
このプロセスが正しく機能するためには、まとまった深い睡眠が不可欠。
つまり、睡眠は脳の掃除時間でもあるというわけです。
こうした5つのミッションをしっかり遂行できてこそ、本当に意味のある「最高の睡眠」が実現します。
次の項目では、そんな最高の睡眠を手に入れるために、実際に何をすればいいのかをお伝えします。
睡眠のクオリティを上げる2つの「体温スイッチ」
「人は寒くなると眠くなる」そんな話を聞いたことがあるかもしれませんが、実はこれは半分正解で半分誤解です。
正しくは深部体温と皮膚温度の差が縮まったときに入眠しやすくなるという研究データが発表されています。
つまり、眠るためには体の中心部(深部体温)を下げる必要があり、そのために皮膚温度を上げて熱を外に逃がす必要があるのです。
この体温調整をサポートする2つの「体温スイッチ」を活用することで、質の高い眠りを自分でコントロールすることができるようになります。
体温スイッチ① 就寝90分前の「入浴」
質の良い眠りをつくるための最強スイッチが、就寝90分前の入浴です。
ポイントは、「皮膚温度を一度上げて、深部体温をゆっくり下げていく」こと。
この「あげて、下げる」プロセスが、入眠をスムーズに導くカギになります。
体は筋肉や脂肪といった遮熱作用のある組織で守られており、さらに深部体温は「ホメオスタシス(恒常性)」によってなかなか変化しません。
しかし、入浴はその深部体温すら動かせる強力な方法です。
具体的には40℃のお湯に15分入浴すると、深部体温が約0.5℃上昇
上昇した深部体温が元に戻るまでにかかる時間は約90分
つまり、就寝の90分前に入浴を済ませておくことで、寝る頃には深部体温がスムーズに下がり、眠気を誘いやすい状態に整うというわけです。
体温スイッチ② 足湯に秘められた驚異の「熱放散力」
「入浴する時間が取れない」
そんな忙しいビジネスパーソンにこそ取り入れてほしいのが足湯です。
入浴は深部体温を上げてから下げるアプローチですが、足湯は直接「熱を逃がす」=放熱のアプローチ。
足には毛細血管が集中しており、熱の出入り口になりやすい
皮膚温度を上げることで、深部体温の低下を促進
入浴よりも体温の変動が少ないため、寝る直前でもOK
深部体温を急激に上げずとも、熱を効率よく逃がすことで、体が自然と「眠る準備」に入るようになります。
入眠をパターン化する脳のスイッチ
質の高い眠りをつくるには、体だけでなく脳の状態も整える必要があります。
睡眠の基本は、「頭を使わない」こと。
言い換えれば眠りの天才は、寝る前に頭を使わない。
とはいえ、「何も考えるな」と言われても、現代人の脳はそんなに単純ではありません。
仕事のこと、スマホの情報、明日の予定。考えたくなくても勝手に脳が働いてしまうのが現実です。
ではどうすればいいのか?
答えは、モノトナス(単調さ)を意識することです。
脳のスイッチ① 「モノトナス」の法則
人間の脳は、単調な状況に対して刺激を感じにくくなるようにできています。
つまり、退屈な状態を意図的に作ることこそ、脳にとっての「眠りのスイッチ」になるのです。
たとえば
ミステリー小説のように脳を刺激する本より、少し退屈なくらいの本を選ぶ
映画や動画を観るなら、ストーリー展開が激しいものではなく、風景や自然音などリラックスできるものを選ぶ
単調な音(波の音、雨音、ホワイトノイズなど)を聞く
こうした「モノトナスな環境」=あえて脳を退屈させる時間をつくることが、睡眠の質をグッと高めるのです。
退屈は、睡眠にとって“最良の友”
日常生活では「退屈」は避けたいものですが、睡眠にとっては、退屈こそが最大の味方です。
眠りを妨げるのは、興奮・緊張・刺激。
それらを静かにオフにしてくれるのが、モノトナスな環境です。
「入浴で体温を調整し、足湯で放熱し、退屈で脳のスイッチを切る」
このパターンを身につければ、あなたの入眠は習慣として定着し、睡眠の質が着実に高まっていくでしょう。
最高の睡眠は、あなたの人生を変える
今回は『スタンフォード式 最高の睡眠』から、
睡眠の質を高めるために特に重要だと感じたポイントをピックアップしてご紹介しました。
睡眠には「脳・体・精神」を整える5つのミッションがあること
深部体温と皮膚温度の差をコントロールする体温スイッチの重要性
「退屈=モノトナス」を活用した、脳の入眠パターン化の方法
これらの知識は、睡眠を「ただの休息」から「人生を整える時間」へと進化させてくれるはずです。
もちろん、本書には今回ご紹介しきれなかった内容もたくさん詰まっています。
日中のパフォーマンスを最大化する覚醒のテクニックや、眠気とどう付き合うかといったヒントまで、多角的に睡眠を捉えた一冊です。
もし少しでも「もっと知りたい」「自分も変わりたい」と思った方がいれば、
ぜひ本書を手に取り、あなた自身の「最高の睡眠」への第一歩を踏み出してみてください。
きっと、明日の目覚めが変わるはずです。